第4回 NTTロジスコの現場力の真髄―LGPS
Enomoto Ikuo
Enomoto Ikuo
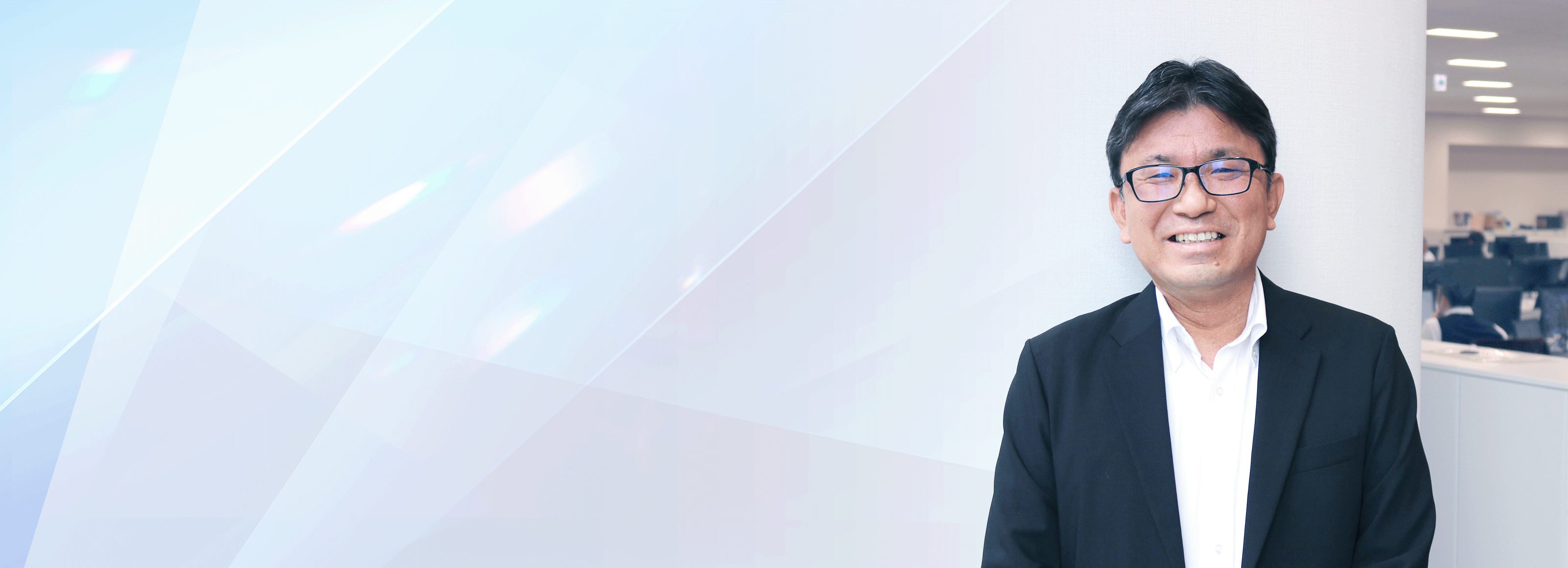
第3回「AIで叶えた倉庫内作業のスマート化」では、「AI画像認識技術を用いた自動検品システム」を用いて倉庫内作業における人手不足への対応策をご紹介しました。今回は、NTTロジスコグループの全国の物流センター運営を包括的に管理し、物流センター業務の標準化や改善活動の推進を担う当社ロジスティクスイノベーション室スマートデザイン部門長 榎本郁生が「NTTロジスコの現場力の真髄―LGPS」について語ります。
NTTロジスコは創立から30年以上が経ちましたが、物流センター運営を行う上でこれまでどのような課題がありましたか。
物流センター業務の設計や運営方法が担当者の経験値によって異なり、作業品質や運営コストが不安定な時期がありました。さらに、不具合が発生した時の再発防止策が問題の本質を捉えたものではなく、対策としてダブルチェックを追加する等、とにかく人手をかけて品質を保とうとするもので、多くの稼働をかけていました。また、個々の業務での失敗事例や反省点が社内で共有されておらず、類似したミスを別の物流センターで繰り返すということもありました。
当社は1994年に日本電信電話株式会社(現NTT)の物流部が独立して誕生したという生い立ちであることから、設立当初はNTTの設備現場で導入されていたQC活動などの改善活動を取り入れていましたが、取組み内容が物流現場にフィットしない部分があったことに加えて、ここでも担当者の能力や経験によって改善活動のレベルが異なり、なかなか全社的に品質を底上げすることができなかったことから、物流現場改善の体系的な仕組みを整備する必要がありました
様々な課題があったのですね。NTTロジスコでは、これらの課題の解決にむけてどのようにアプローチしましたか。
2009年に製造業で導入されていたTPS(トヨタ生産方式)の考え方を全国の物流センター業務に導入しました。5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)をはじめ、異常が発生しない(異常を即座に認識できる)仕組みづくりや「7つのムダ(※1)」を基にした作業工程の見直し(ムダ取り)等を全社統一のルールとして導入し、その後それをベースとして物流業により適した形で発展させたNTTロジスコオリジナルの改善手法となる「LGPS® (LOGISCO Production System) 」を体系化しました。物流業務改善を設計(Plan)、運用(Do)、管理(Check)、改善(Action)のPDCAに整理し、ハンドブックとしてまとめNTTロジスコ標準の改善手法として定義しました。ハンドブックには過去の失敗事例を「黒歴史」として記載し、同じ失敗を繰り返さないよう業務内容別に非常に細かくノウハウを盛り込んでいます。LGPSはまさに「安全と品質を確保した上で低コストな物流オペレーションを実現するロジスコ独自のノウハウ」の集大成です。
(*1):トヨタ生産方式から生まれた製造現場を効率化しより良くするための手法のこと。加工、在庫、造りすぎ、手待ち、動作、運搬、不良・手直しの7つの視点からムダを定義している。

LGPS導入により物流センター運営にはどのような効果をもたらしましたか。
個人の経験や知識に頼った物流設計や改善活動を解消できたことで、安全、高品質、低コストな物流センター運営を全社の共通言語として実現することができるようになりました。
LGPSでは業務設計から日々の運営・管理、改善までを一連のサイクルで標準化しているので、全国どこの物流センターに行っても常に倉庫内は整然としてきれいです。これが意味するところは、倉庫内は常に正常な状態に保たれていて、異常があるとすぐに検知できるので即座に是正できるということです。これにより従業員が安全かつ快適に働ける職場環境と高品質で効率的な物流センター運営が実現できるのです。また、標準作業が明確に定義されているので、従業員全員があるべき姿の共通認識を持つことができ、改善活動が活性化したことで品質や作業性も向上しました。不具合を発生させてしまった場合も、標準の分析手法で真因追究を行うことにより、個々の事象に対してより効果的な再発防止策を講じることができるようになりました。
LGPSの他社と差別化できる要素について教えて下さい。
パート従業員を含め新規入職者はまず初めにLGPSの基礎研修を受けるので、社員だけにとどまらず全従業員に物流センター業務の基本理念が浸透していることと、さらには一人ひとりがきちんと改善手法を習得し、実行できることが挙げられると思います。物流センターのパート従業員から改善提案があがることは珍しくありませんし、全員参加型で取り組めることが当社の強みであり、これにより高品質かつ低コストなオペレーションが実現出来ています。NTTロジスコでは年1回「優良事例報告会」という全国の物流センターの改善活動を発表する場がありますが、発表を通じて従業員が決して受け身ではなく自発的に改善に取り組み物流現場の課題を発信している様子を見ていると、従業員の改善に対する意識はもはやNTTロジスコの文化として根付いていると感じることが出来ます。

LGPSは今後どのように進化する予定ですか。
次のステップは物流センターの品質とコストを数値で可視化し、全社統一のKPIで評価することです。これまで物流現場毎に実施していたコスト分析を進化させ、全社の仕組みとして標準項目は自動化することで、より高速に改善のサイクルを回すことを目指します。この取り組みは2024年から開始したところですが、今後LGPSとして定義していきたいと考えています。
また、今後の物流現場では自動化とロボティクスの導入が重要な要素となりますが、これを実現するためには定量的なデータが必要となります。物流業務の設計時に分析したお客様の数値情報と日々のオペレーションから得られるデータを活用したロボットと人が共存する最適な物流センターの運営方法、データに基づく最適な自動化設備とロボティクスの導入方法をLGPSに定義することで、当社の物流基盤であるLOPOCE®(※2)をより強固なものにしていきたいです。
(*2):「Logistics Process Optimization and Co-evolution Platform(物流プロセス最適化&共進化プラットフォーム)」の略。NTTロジスコの強みである5つのリソース(AI・ICT、ロボティックス、ネットワーク、ナレッジ、SCM)から収集したデータを相互に統合・活用することにより、サプライチェーンの様々な課題を解決することで、お客様の物流改革・DXを実現し、パートナー企業様と共に進化させる物流基盤。
今後の榎本さんの意気込みを教えてください。
物流の入出荷等のデータは物流センター内の改善活動だけではなく、お客様のサプライチェーン上の課題解決を実現するための貴重な情報であると考えています。3.5PL®(※3)事業を展開するNTTロジスコで、お客様のサプライチェーン上の課題解決等の4PL事業領域を担う当社のSCMコンサルティング室とも連携し、物流センター内の定量情報を活用することにより、総合的な物流センター運営を行う3PL事業領域を超えサプライチェーン全体の最適化に貢献したいと思っています。
お客様の物流業務やサプライチェーンの改革を推進していくためには、弛まぬ改善を継続する現場力が必要不可欠であり、その現場力の源泉こそがLGPSの考え方にあると考えています。NTTロジスコグループの財産であるLGPSは今あるものが完成形ではなく、今後も新たな技術やノウハウを取入れ、現場発信の改善力にさらに磨きをかけることにより進化していくものです。
(*3):お客様企業の物流戦略の策定(4PL)から実際の物流運営(3PL)までのサプライチェーンに関わる様々な課題解決を実現するNTTロジスコ独自の事業モデル。

ありがとうございました。
榎本 郁生(えのもと いくお)
ロジスティクスイノベーション室 スマートデザイン部門 部門長、物流技術管理士
LGPSをベースとした全社の品質の向上や改善のほか、物流現場の見える化の推進、ロボティクスや新技術の導入推進、物流拠点の維持や新設等を担当
